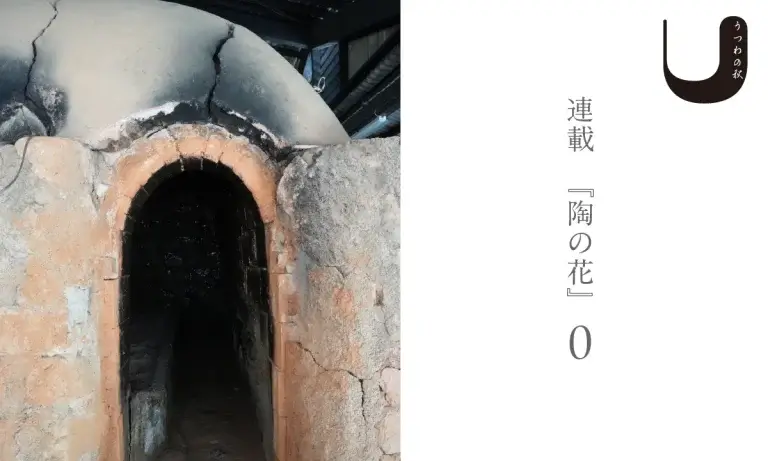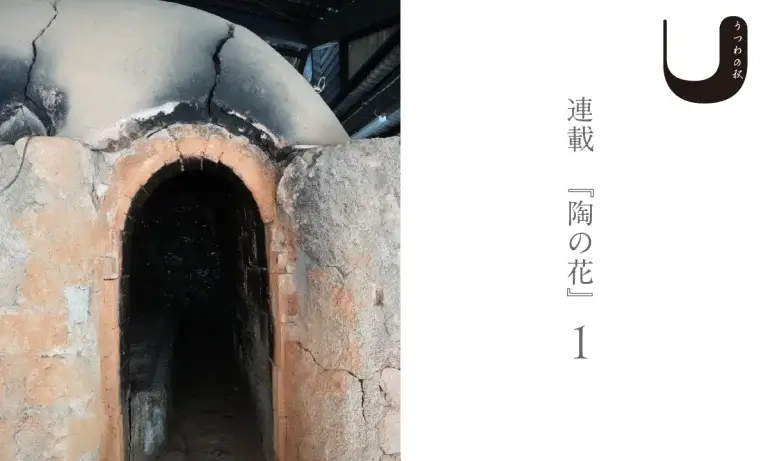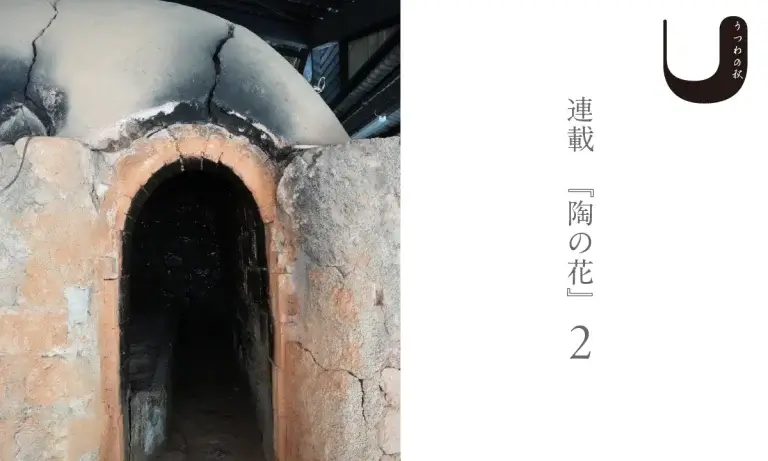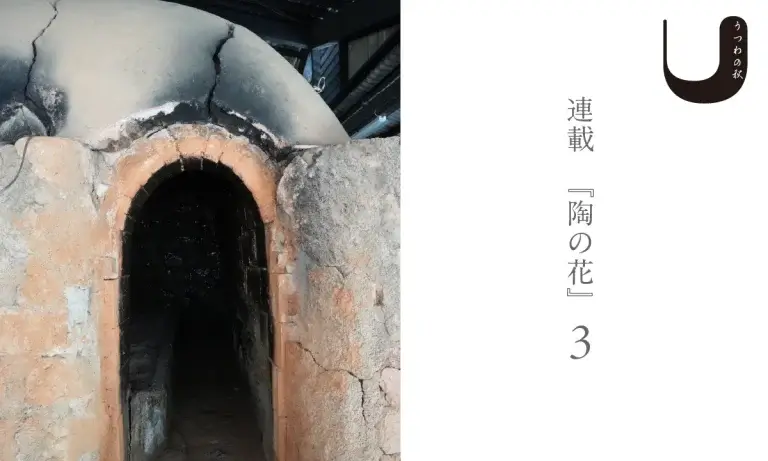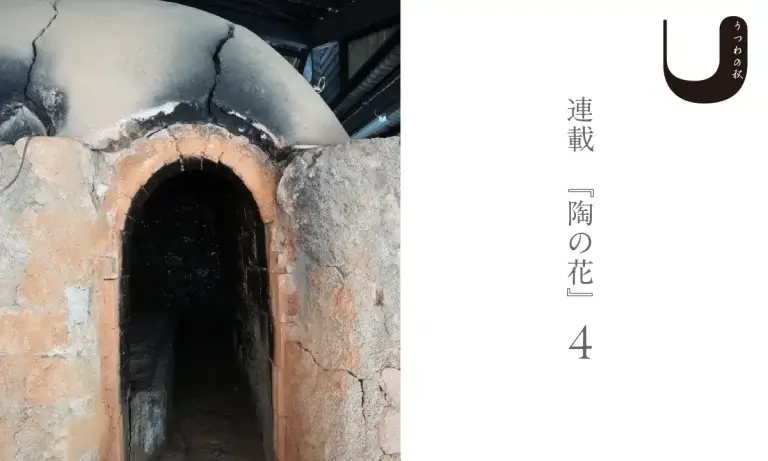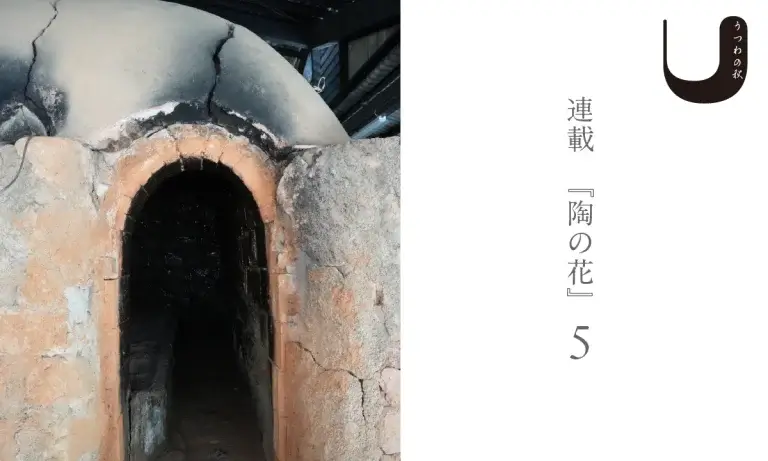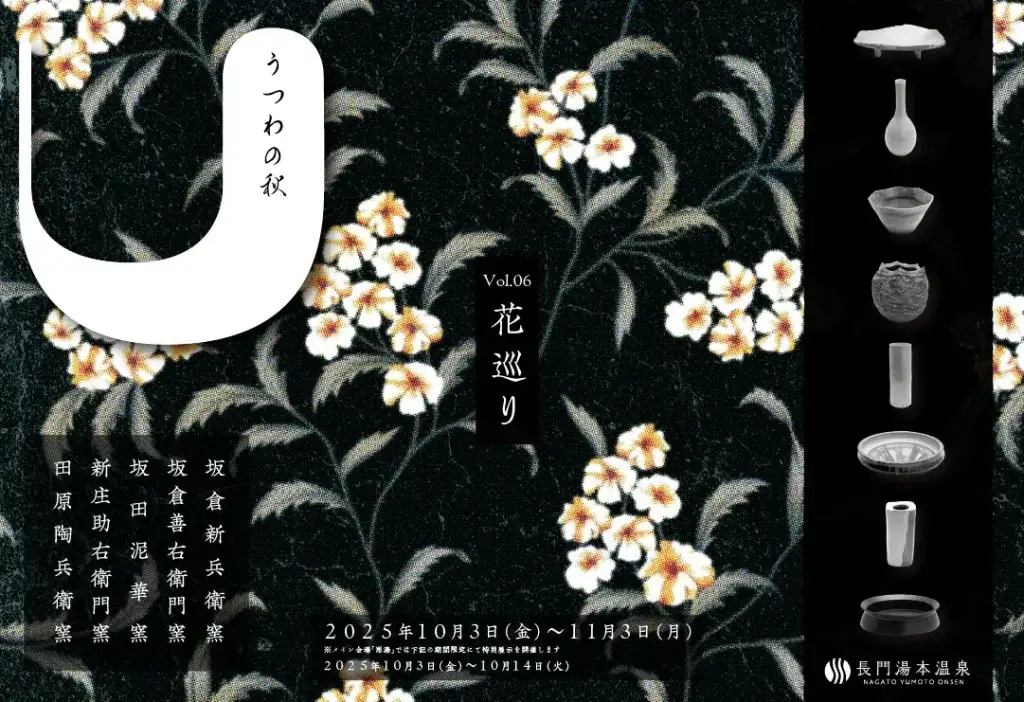車は新山口駅から1時間弱、国道316号線をゆく。やがて「湯本」の看板が見える三叉路を左へ曲がると長門湯本温泉街へと降りてゆくことができる。
川に架かる橋を渡るといよいよ温泉街の入り口のようだ。
K女史によれば、今回は最初に湯本温泉旅館協同組合の事務所に行くことになっているという。
ここで第一村人ならぬ、第一温泉街人となる人たちと出会うことになっていた。
湯本温泉旅館共同組合の瀧口さんと、長門湯本温泉まち会社の木村さんである。
ここで彼女彼等のお話を書き続けると、一行に連載が終わらなくなる様子になりそうなので、以後所々でご登場いただこうと思っている。
これは後々わかったことなのだが、淑女瀧口さんも、地方豪族の王子様のような木村さんも、素晴らしいキャリアを持ちながら、この長門湯本温泉エリアの活性やまちづくりに魅力を感じ心血を注がれている愛すべきお二人なのだ。
さてさて、日本各地の温泉地は多々あれど、最も温泉地にお似合いの風景と言ったら何だろう?
「浴衣に下駄」はもちろんだが、、、私にはそれが「川」と「橋」に思えて仕方がない。
江戸時代の「温泉番付」なるものに名を連ねる温泉地の多くも川の流域に沿った場所に位置するものが多い。
有馬、草津、城崎に那須に下呂、などなど。
私の住む東京近郊で言えば、箱根や修善寺だって川と橋が似合う温泉地だと思っている。
それに、「橋」や「川」がある温泉地を舞台にした随筆や小説、映画も大正昭和の時代にはたくさん愛された。どこか艶っぽく、旅情を喚起するシグナルのような気もしてくる。
平成が過ぎ、この令和の時代にもそれはきっと同じなのではないかとさえ私は感じているわけなのだ。
「旅情」という感情の解放。
大地から溢れる泉である「湯」に浸かるという生命の歓喜。
常ならず流れ行く「川」のほとり。日常とは異なる世界への導線である「橋」。我ゆくは魅惑の温泉世界。願わくばそんな雰囲気が温泉街にはあってほしい。
おっと、やや私感が過ぎた。
この長門湯本もまさにその「川」と「橋」が魅力的なのだ。
そして、ここ湯本に流れる川の名は「音信川」と書いて「おとずれがわ」と読むらしい。
K女史、淑女瀧口さん、木村王子と連れ立って、湯本の街中を流れる川沿いを私は歩いている。
「音信?つまり〝便り″ってことなのか、、、?」と思っていると、淑女滝口さんが「昔、この温泉街で働く女性がなかなか会えない恋人に手紙を書いて川の流れに託して手紙を川に流したっていう伝説からこの温泉街を流れる川を音信川としたとも言われているんです」と教えてくださった。
なんと、いいじゃないか。あるではないか。
温泉街にぴったりな旅情的恋話が。行くあてのない恋、悲恋とまでは言わずとも、切なき蒼茫が。
そうこなくっちゃ、温泉地。
いわゆる史実の正否ではなく、このような物語が川の名の言われになっているということ、また、その物語を「川の名」として育んできた人々や街であることが大きな価値であるように思う。
なぜなら、この「音信川」は国土地理院の地図での河川名は「深川川(ふかわがわ)」なのだ。
そもそも深川川は、山口県長門市と美祢市の境にある天井山(標高 602m)に源を発し、長門市を貫流して日本海の深川湾に注いでいる二級河川となっている。
しかし、この長門湯本温泉街を流れる時にだけ、深川川はその姿を「音信川(おとずれがわ)」と変えるのだ。なんともロマンチックではないか。
この温泉地に暮らし、旅した先人たちの思いの表層がそこには映っているような気がするのだ。
我々人類の直接的祖先がアフリカのサバンナを二足歩行で出奔したのがおよそ700万年前。言葉の誕生は7万年ほど前と言われている。文字の誕生はわずか5000年前だ。
人類民俗学的な観点からすると、つまり言葉は「音」であった時間の方が「文字」となった時間よりはるかに長いのだ。
言葉は文字表記ではなく、その呼び名、つまり「音」にかつての記憶や痕跡を多く残していると考えることは、やぶさかなことではない気がするのだ。
充てた漢字(文字)ではなく、呼び名(音)にこそ、先人からの文化が宿っている、とも言える。
であるならば。
表記の「音信」は「便り」でありながら、もう一方の「おとずれ」は、この温泉が湧く地への幾許もの人の来訪往来、つまり「おとずれる」の痕跡でもあるかもしれず。
はたまた、鳥の「さえずり」のように、想う誰かの声を感じる「おとずり」かもしれず。
ひょっとすると、日々ゆく川の流れは絶えずして川中を流転する小石や魚、風に揺れ草花がスレあう「音スリ」なのか。
はたまた、湯場の誰かと袖擦れ合う「スレル」かもしれず、、、
そんな風に自由で、そしてどこか生命の機微に触れるような温泉地物語の想像は私のような通りすがりの旅人にとってとても心地の良いものでもある。
これこそ温泉街の川風情だとも思う。
温泉地に流れる川には、「情緒」が染み付いている。
それを感じられる長門湯本の川風情は、ずっと眺めていられる物語の宝庫のようなものだ。
そんなことを考えながら私は音信川のほとりを歩いていた。
気づくと腹の虫が鳴き始めている。
時計は、正午を少し回った頃だった。
「さぁ、昼飯は何を食べようか」
田中 孝幸